
CONCEPT自然素材でつくるデザイン住宅
自然素材をふんだんに使った家で、快適な生活を送りませんか。
シセイハウジングでの家づくりのコンセプトは「自然素材でつくるデザイン住宅」
選りすぐりの素材が織りなす自然のハーモニーが、日々の暮らしを彩ります。
自然素材での家づくりは家族の健康にも関係しているので、安心した暮らしを送ることができます。
さらに、当社ではデザインにもこだわった家づくりを行っています。
家族の「現在」だけではなく「未来」を見据えた家づくりをご提案。
変化し続けるライフスタイルに合った家づくりで、何年先も快適に過ごせる家を実現いたします。
自然を感じられるマイホームで、快適な暮らしをいつまでも送りましょう。

WORKS施工実績

PRICEご予算に合わせた家づくり
マイホームは、一生に一度の大きなお買い物。
皆さんのご予算やご希望に合わせて、最適な家づくりを提案します。
皆さんのマイホームに対するワガママを全てお伝えください。

PERFORMANCE安心して住み続けられる家を
どんなにかっこいい家を建てたとしても、性能が悪ければ快適な暮らしを
送ることができません。
当社では、安心して暮らしていただけるよう、
性能にもこだわって家づくりをしています。

AFTER MAINTENANCE快適な暮らしをいつまでも
家は完成してからが始まりです。
当社では、定期点検やアフターサービスも充実しています。
実際の暮らしの中で悩み事や不安なことがある場合は、
お気軽にご連絡ください。
NEWS&BLOGニュース&ブログ
-
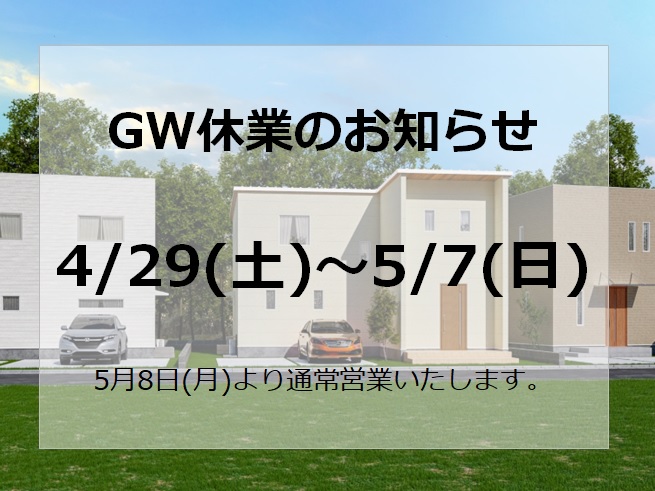
GW休暇のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ではございますが、 4月29日(土)~5月7日(日)まで お休みとさせていただきます。 5月…
Long Name Here12か月前
-

#154 あらたな分譲プロジェクト 緑豊かなエコの街「大木町」の魅力♪
緑豊かな美しいエコの街「おおきまち」3区画分譲地販売中です!ZEH基準クリア!自然素材でつくるデザイン住宅!高性能+安心の耐震等級3の自然素材でつく…
Long Name Here1年前
-
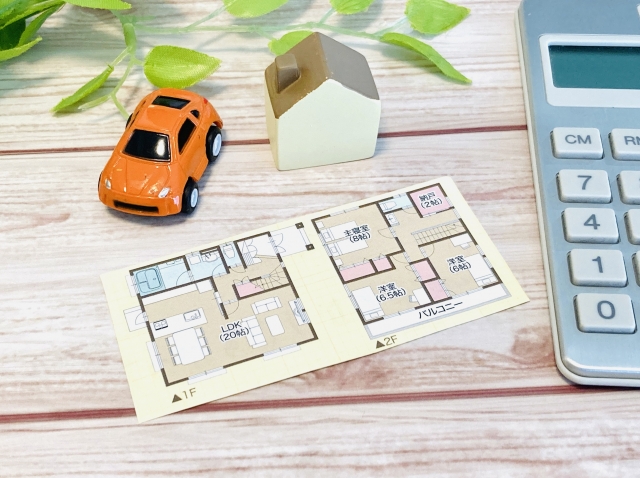
#153 意外に重要な「駐車スペース」の考え方
駐車スペースの作り方で車の止めやすさは大きく変わります。限られた土地の広さを有効的に、毎日の生活がしやすい環境へ作っていくためにもぜひ駐車スペースの…
Long Name Here1年前
















